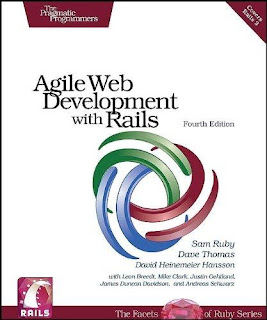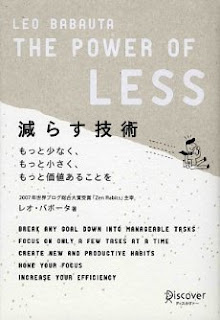米国留学中にガッツリ読まされた本です。Modern Operating System (3e) は日本語訳がまだなので、もしこれから読むならこちらの方を読んだ方が良いと思います。
本書は、OSの概念から始まり、Process や Filesystem,Memory や I/O などの基本的な機構を一つずつ章分けして解説している本になっています。各章末にある問題は、実際に考えてみるととメチャクチャ面白いので、もしよければ章末問題もやってみると良いと思います。
少し全般的な話になっていまいますが、どうしても邦訳だと変な日本語になってしまいがちだと感じています(英語→日本語の変換がそもそも本質的に難しい作業なのだと感じています)。ただ、実際に原著の方もそんな難しい言葉を使っているかというと、全然そんなことはなくて、かなり丁寧に分かりやすい言葉を(恐らく意図的に)選んで書かれていました。なので、多少英語が苦手でも、こちらの原著を読んで理解した方が、翻訳によるノイズで時間を無駄に割くこともなくなるかな、と個人的には思います。
翻訳された本の全てが悪いとは全く思っていませんが、一方で、やはり専門書の翻訳はかなり厳しいモノがあるなーと、実際に xv6 の翻訳にチャレンジしてみて実感しました。
ご参考になれば幸いです。